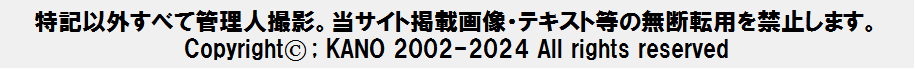|
 |
 |
 |
| 事業用車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【写真へ】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救援車 クモエ21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クモエ21800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.226‐9 1991年7月25日 クモエ21800 佐久間レールパーク |
側面中央の大きな扉と前面のオフセットした扉が印象的で一度見たら忘れない強烈なお顔。連結器は双頭式双頭式で頼もしい。このクモエ21800は1975年にクモエ008を長野工場で低屋根化して改番されています。このとき前位側にあったパンタグラフを後位に移設しています。神領区に所属していましたが1987年に廃車となり保管,写真のように佐久間レールパークに展示されていましたが,その後展示車輌入れ替えに伴い惜しくも解体されてしまったようです。また見に来ようと安心していましたが全く油断できません。 (2023/04/02ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牽引車 クモヤ22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【写真へ】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クモヤ22113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.64‐32 1984年8月1日 クモヤ22113 浜松工場 |
115系3連の先頭に立つクモヤ22113。最後部にはクモヤ90053が控えています。 (2022/02/14追加) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.64‐33 1984年8月1日 クモヤ22113 浜松工場 |
この夏最大のイベント,浜松機関区きかんしゃ大集合の時に撮影。浜松工場で115系の牽引に活躍するクモヤ22113。塗装も新しく美しい姿を見ることができラッキーでした。 (2023/04/02ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クモヤ22201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.66‐15 1984年8月19日 クモヤ22201 浜松機関区 クモヤ22201‐22203は,牽引車代用として使われていた,木造車を鋼体化したクモニ13形を1970年に改番したグループで,新性能車は制御できませんでした。外観,内装とも荷物車時代のままとなっています。 (2023/04/02ワイド化) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配給車 クモル23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【写真へ】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クモル23050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.64‐22 1984年8月1日 クモル23050 浜松機関区 一度見たら忘れられないインパクトの強い車輌。このクモル23050は1961年に国鉄豊川分工場でモニ13027から改造された配給制御電動車で,荷重は有蓋室5t、無蓋部5t,無蓋部は木製アオリ戸になっています。正面は前後ともHゴム支持の傾斜のついた2枚窓で,最大の特徴となっています。1985年に廃車となりました。 (2023/04/02ワイド化) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.66‐17 1984年8月19日 クモル23050 浜松機関区 |
浜松で行なわれたきかんしゃ大集合で展示されたクモル23050+クエ28100+クモヤ22201という個性派揃いのDeepな編成。なかなか味わい深く,鉄コレ用モータを使って模型化しようかなどと考えている昨今でございます。 (2023/04/02ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救援車 クエ28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【写真へ】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエ28100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.66‐16 1984年8月19日 クエ28100 浜松機関区 |
写真のクエ28100は飯田線用として山岳用の仕様となっており,前後妻面に観音開きの大形扉が設置され,前照灯が増設されています。半室式の運転室が前後に設置されましたが、助手席側の乗務員扉はなくサイドから見ると片運に見えます。パンタグラフ・MG
も搭載されていません。中間に挟まっているので左側に増設された照明を持つ正面が拝めません。 (2023/04/02ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.64‐3 1984年8月1日 クエ28100 浜松機関区 |
上の写真の逆サイド。運転室部の増設された照明が見えます。乗務員扉の形状が上の写真と異なります。 (2015/04/25追加 2023/04/02シャドー調整) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牽引車 クモヤ90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【写真へ】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クモヤ90004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.28‐13 1983年12月27日 クモヤ90004+クモヤ145‐108 阪和線 山中渓→紀伊 |
この1つ前のコマの分析により右側はクモヤ145‐108と思われます。一方クモヤ90の番号ですが,4つの扉に着目すると,左側から黒Hゴム,桟のある原形扉,白Hゴム,白Hゴム,となっており,パンタから運転室窓外側への高圧配管も目立ちます。この特徴から,天ヒネのクモヤ90004と見て問題なさそうです。この車両は制御電動車モハ63170として1945‐1946年に川崎車輌で製造されました。その後,63系の更新修繕で日本車輌支店にて中間電動車モハ72064に改造され,さらに郡山工場でクモヤ90004に改造されています。 (2011/11/06追加 2023/04/02ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クモヤ90014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.N7806‐5(H.K) 1978年7月 クモヤ90014 東海道本線 住吉→摂津本山 当時中学生だった弟のH君がハーフサイズのオリンパスPen Fで撮影した,本山の大カーブでのクモヤ激走シーン。擦り切れるようなツリカケモータ特有の唸り音がよみがえります。東海道・山陽緩行線は1976年2月26日にて旧型国電の運用は終了しており,ぶどう色のツリカケ電車はクモヤ,クモルのみと貴重な存在になっていました。番号不明でしたが,運転士側窓外側に高圧配管があること,運転士窓上から避雷器に向けて配線が出ておりこの位置に特徴があること,などから実車写真と見比べてクモヤ90014がこれらの特徴と一致することが判りました。クモヤ90014は元は1948年に近畿車輛で製造された制御電動車モハ63844です。1952年前後の更新修繕で,汽車会社にて中間電動車のモハ72314に改造されました。さらに大井工場にてクモヤ90014に改造され,大タツに所属していました。 (2023/04/02ワイド化) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クモヤ90052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.133‐32 1986年8月6日 クモヤ90052 沼津機関区 |
沼津機関区にぶどう色の機関車を並べた展示会があり立ち寄ったときの1枚。熱中症で倒れそうに暑い日でした。クモヤ90の50番台は新性能車両と旧性能車両のブレーキ装置を自動的に切り替える機能が付けられた牽引車ですが,のちに0番台車にも同じ機能が取り付けられたことから,実質的な違いはなくなっています。クモヤ90052は一時豊橋区に常駐し,クモハ12041と2両でイベント列車として運転されたり,トロッコ列車の入れ替えや,冬期に飯田線北部の霜取り電車として活躍しました。1995年1月13日付けで廃車になっています。 (2023/04/02ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クモヤ90053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.64‐31 1984年8月1日 クモヤ90053 浜松工場 115系を牽引するクモヤ90。やはり現役で活躍する姿を見るのが嬉しい。銘板の数が深い歴史を物語っています。番号不明でしたが妻面の銘板には (郡山工場) (日本国有鉄道) (日本車輌) (汽車會社) と記載されており,この条件に合うクモヤ90を探索すると90053しか該当しませんでした。実車写真とも相違なく特定できました。クモヤ90053は,元は汽車会社にて1947年度に製造されたモハ63687であり,その後日本車輌支社にてモハ72261に中間車化改造され,郡山工場でクモヤ90053に改造され,静シスに配置されていました。 (2023/04/02ワイド化) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クモヤ90202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.144‐25 1987年3月17日 クモヤ90202+クモヤ90 東海道本線 高槻←山崎 |
山崎の有名撮影地を2両で通過するクモヤ90202先頭の2両編成。クモヤ90の0番台と50番台車はモハ63改造のモハ72を種車としていますが,クモヤ90の100,200番台車はモハ72として新製された車両が種車となっています。クモヤ145同等の車体ですが,旧性能車であるためぶどう色2号をベースとし,黄5号の警戒色となっています。 (2015/01/18追加) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クモヤ90803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.203‐35 1991年2月8日 クモヤ90803 大糸線 南小谷 |
115系を牽引するクモヤ90803。能登のSLときめき号撮影の折,1人でバルブ。上の写真とは打って変わって凍えそうでした。
クモヤ90800番台は中央本線用の低屋根車です。このうち90801は全低屋根車でDT14形台車を履いています。90802以降はパンタ部のみ低屋根車ですが,写真の90803のみダブルパンタグラフを装備し両車端を削った凸形で,側窓もモハ72時代の上中段が1枚窓化されているのが特徴となっています。 (2023/04/02ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.203‐34 1991年2月8日 クモヤ90803+115系3B 大糸線 南小谷 |
編成全体。115系3両を牽引しています。 (2023/04/02追加) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牽引車 クモヤ91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【写真へ】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クモヤ91003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.60‐34 1984年7月22日 クモヤ91003+485系5B 東海道本線 高槻→山崎 |
百山踏切の定点にて,485系5両を牽引するクモヤ91。ナンバー不明でしたが,非パンタ側運転台下に銘板が3枚付いていることからクモヤ91003であると特定できました。因みに91000は後部標識灯の下に2枚,91001は標識灯横に2段で4枚,91002は標識灯下に2枚とすぐ横のステップ上下に2枚の計4枚で,全て異なっていました。ありがたい。 (2023/04/02ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交直流牽引車 クモヤ441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【写真へ】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クモヤ441‐2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.172‐22 1989年10月17日 クモヤ441‐2 常磐線 日立→小木津 |
屋根上は機器出し入れ用として開閉可能になっているため通風器がなく,パンタグラフと検電アンテナ,汽笛,無線アンテナ程度しか載っておらずすっきりしています。車体は新製されていますが側扉に種車の面影が残っています。 (2023/04/30追加) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.243‐16 1991年10月13日 クモヤ441‐2他 勝田電車区 |
403系,651系と並ぶクモヤ441‐2 (2023/05/19追加) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.347‐19 1994年11月12日 クモヤ441‐2 常磐線 勝田 |
勝田に甲種輸送されてきた試験車両Try‐Xを勝田電車区まで引き上げるためEF81に代わって登場したクモヤ441‐2。ホームにはギャラリーがいっぱい。 (2023/06/25追加) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クモヤ441‐5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.172‐23 1989年10月17日 クモヤ441‐5 常磐線 日立→小木津 |
485系2ユニット4両をサンドイッチしてサポートする交直流牽引車クモヤ441。右側がクモヤ441‐2,手前がクモヤ441‐5。 (2023/04/30追加) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007年11月3日 ページ新設 2023年4月2日 写真ワイド化完了 2023年4月2日 キャプション欄左右入替完了 2023年4月4日 Safariで半角数字列が電話番号リンクされるのを無効化 2023年4月4日 各形式毎に改造車一覧表を追加 2023年4月4日 改造車一覧表から各写真へのリンクを設置 ■参考文献 鉄道ファン Vol.36 No.417 ロクサン形電車とそのファミリー 1996年1月 交友社 沢柳健一 旧型国電50年Ⅱ JTBキャンブックス Wikipedia 国鉄63系電車 Wikipedia 国鉄72系電車 Wikipedia 国鉄クモエ21形電車 Wikipedia 国鉄クモヤ22形電車 Wikipedia 国鉄クモル23形電車 Wikipedia 国鉄クエ28形電車 Wikipedia 国鉄クモヤ90形電車 Wikipedia 国鉄クモヤ91形電車 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
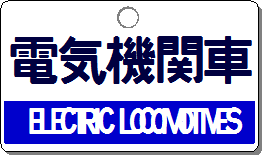 |
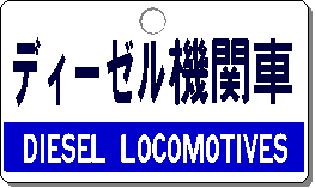 |
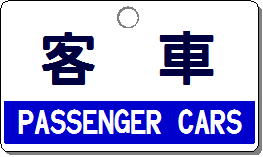 |
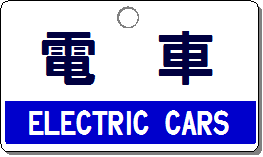 |
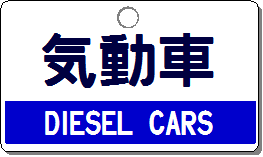 |
 |
|---|