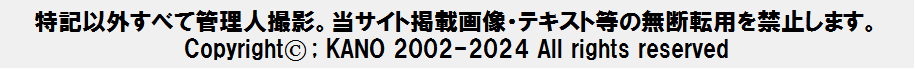|
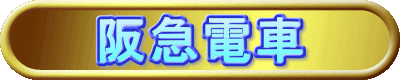 |
 |
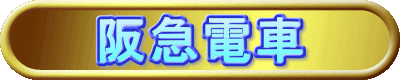 |
| 7000系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7000-7027, 7030-7037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.N8106-11 1981年9月2日 7001F 7001他 6両 特急 梅田行 神戸線 西宮北口 梅田 7001-7501-7561-7571-7601-7101 須磨浦公園 ポートピア81のヘッドマークを付けた登場間もない頃の7001F。1980年に製造された当初の7001Fの編成は6両で,その後1984年に7551,7581を加えて7001-7501-7551-7561-7571-7581-7601-7101と8両化されました。4M4Tだと中間4両がT車で床下が何にもなく,ちょっと頼りなく感じたものです。 (2024/03/20ワイド化) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.N8208-21A 1982年5月下旬 7004F 7004他 8両 普通 三宮行 神戸線・今津線 西宮北口 |
梅田 7004-7504-7554-7564-7574-7584-7604-7104 三宮 手前から3番目の線路は神戸方面行きの主に普通列車用で,Hマークを輝かせて7004Fが神戸に向かいます。7004Fは1981年7月31日に製造された8両4M4T。 (2024/03/20 本ページに追加) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.58-14 1984年7月16日 7011F 7011他 8両 新製車試運転 京都線 水無瀬→上牧 |
正雀 7011-7511-7651-7661-7671-7681-7611-7111 桂 新製された宝塚線の7011Fが京都線にて試運転中。この7011Fからアルミ車体となっています。床下機器と自連が独特の青みがかったグレーに塗られています。これは現在では見られない特徴のひとつです。床下機器は鉄粉等で汚れるのでわかりづらいのですが新製車や塗装を実施した出場車は顕著に違いが出ています。正雀出場車の試運転は正雀-桂間で行われています。 (2024/03/20ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D70s_060103-0 2006年1月3日 7003F 7003他 8両 特急 梅田行 神戸線 芦屋川 |
梅田 7003-7503-7553-7563-7573-7583-7603-7103 高速神戸 7003F,No.50-38から約22年が経過し,編成は組み替えられています。7003は10両対応で電気連結器付き密着連結器を装備し,上部がアイボリーに塗られていますが,マルーンとアイボリーとの塗り分けラインは先駆者たる6300系とは異なり,正面表示幕の額縁の上端となっています。 (2024/03/20ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_111113-87 2011年11月13日 7008F 7008他 8両 普通 三宮行 神戸線 芦屋川 |
梅田 7008-7508-7558-7568-7578-7588-7608-7108 三宮 9000系の前面形状に似たスタイルにリニューアルされた7008Fが芦屋川を出発。方向幕がLEDになっており文字が飛んでしまう,高速シャッター泣かせの車両です。 (2024/03/20ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_111113-90 2011年11月13日 7007F 7007他 8両 普通 梅田行 神戸線 芦屋川 梅田 7007-7507-7557-7567-7577-7587-7607-7107 三宮 こちらはこのタイプのリニューアルが最も早く施工された7007Fです。この写真もLED方向幕が飛んでしまいました。 (2024/03/20ワイド化) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_111113-104 2011年11月13日 7027F 7027他 8両 普通 三宮行 神戸線 芦屋川 |
梅田 7027-7527-7774-7767-7777-7764-7627-7127 三宮 7027Fの梅田方は電気連結器を装備しています。 (2024/03/20ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_111113-109 2011年11月13日 7021F 7021他 8両 特急 梅田行 神戸線 西宮北口 梅田 7021-7521-6671-7761-7771-6681-7621-7121 高速神戸 6000系を挟んだ8両で特急仕業に就く7021F。 (2024/03/20ワイド化) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_111113-138 2011年11月13日 7023F 7023他 6両 快速特急 河原町行 嵐山線 嵐山 桂 7023-7523-7763-7773-7623-7123 嵐山・河原町 嵐山に到着した直通特急はあたごヘッドマークのまま,今度は快速特急で河原町に向かいます。 (2024/03/20ワイド化) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_120101-154 2012年1月1日 7007F 7007他 8両 特急 梅田行 神戸線 芦屋川 |
梅田 7007-7507-7557-7567-7577-7587-7607-7107 三宮 芦屋川を通過する7007F (2012/1/8追加 2024/03/20ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_120103-213 2012年1月3日 7022F 7022他 8両 普通 三宮行 神戸線 十三 |
梅田 7022-7522-7676-7762-7772-7666-7622-7122 三宮 この日は阪急の撮影がてら余剰18切符の売却と交通科学博物館に行きました。阪急十三は何名か鉄道ファンが初詣マーク付き列車を撮影していました。 (2024/03/20ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_120103-218 2012年1月3日 7011F 7011他 8両 急行 梅田行 宝塚線 十三 梅田 7011-7511-7651-7661-7671-7681-7611-7111 宝塚 美しく整備された7011F,梅田方の7011には電気連結器を装備。 (2024/03/20ワイド化) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_120103-224 2012年1月3日 7003F 7003他 8両 特急 新開地行 神戸線 十三 |
梅田 7003-7503-7553-7563-7573-7583-7603-7103 新開地 神戸線の列車は大半が7000系で運転されていますが,9000系に似せた改造も進んでおり,アイボリー2色塗装されているものの,この形態の7000系は徐々に少なくなるので,今のうちに撮影しておきたいと思います。(2024/03/20ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_120103-236 2012年1月3日 7013F 7013他 8両 特急 新開地行 神戸線 十三 |
梅田 7013-7513-7653-7663-7673-7683-7613-7113 新開地 カメラの位置を下げたので上の写真よりはバランスが良いと思います。このホームは京都線側もこの構図も水平の取り方が難しく毎度苦労しています。 (2024/03/20ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_120103-244 2012年1月3日 7000F 7000他 8両 特急 新開地行 神戸線 十三 |
梅田 7000-7500-7550-7560-7570-7580-7600-7100 新開地 7000Fのまともな写真を撮影するのは初めてでした。 (2024/03/20ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_130504-002 2013年5月4日 7000F 7000他 8両 普通 梅田行 神戸線 岡本→芦屋川 |
梅田 7000-7500-7550-7560-7570-7580-7600-7100 三宮 保久良神社祭礼で田邊地区の地車(だんじり)が踏切待ち。 (2022/03/22追加) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_131228-28 2013年12月28日 7006F 7006他 8両 特急 新開地行 神戸線 梅田 梅田 7006-7506-7556-7566-7576-7586-7606-7106 新開地 2014年の干支である午をあしらった初詣ヘッドマークを掲出した7006Fの8両編成。 (2014/01/11追加 2024/03/20ワイド化) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_131228-43 2013年12月28日 7006F 7006他 8両 特急 新開地行 神戸線 梅田 |
梅田 7006-7506-7556-7566-7576-7586-7606-7106 新開地 上と同じ編成。7000系は登場から30年以上になりますが古さを感じません。 (2014/01/11追加 2024/03/20ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_131228-42 2013年12月28日 7009F 7009他 8両 普通 三宮行 神戸線 梅田 梅田 7009-7509-7559-7569-7579-7589-7609-7109 三宮 こちらは普通運用に就く7009編成。 (2014/01/11追加 2024/03/20ワイド化) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_180815-519 2018年8月15日 7009F 7009他 8両 普通 梅田行 神戸線 六甲 |
梅田 7009-7509-7559-7569-7579-7589-7609-7109 神戸三宮 この編成が戻って来るのを六甲で待ち伏せ。 (2018/09/17追加) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_190430-149 2019年4月30日 7018F 7018他 8両 急行 梅田行 宝塚線 十三-梅田 |
梅田 7006-7506-7566-7576-7606-7106 河原町 宝塚線の7018F。外観の大きな改造はされていません。 (2019/06/23追加) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7100-7127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.N8208-20A 1982年5月下旬 7001F 7101他 6両 普通 今津行 神戸線・今津線 西宮北口 |
今津 7001-7501-7561-7571-7601-7101 宝塚 平面交差だけでなく手前に見える構内踏切も魅力的でした。 (2024/03/20 本ページに追加) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.N8208-22A 1982年5月下旬 7001F 7101他 6両 普通 宝塚行 神戸線・今津線 西宮北口 |
今津 7001-7501-7561-7571-7601-7101 宝塚 上と同じ編成,6両時代の7001F,4M2T。 (2024/03/20 本ページに追加) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.N8214-26 1983年1月4日 7006F 7106他 6両 特急 梅田行 神戸線 芦屋川→夙川 |
梅田 7006-7506-7566-7576-7606-7106 須磨浦公園 6両編成の7006F。左側に見えるのが甲陽線に繋がる側線で,前方の西宮方から来た回送電車は一旦手前の芦屋川方向で停車,後退して渡り線にて上り線に入り,夙川駅の上り線に停車,さらにスイッチバックして左側の側線に移り,左前方向に進んでようやく甲陽線に入ることになります。7006Fはその後,T車2両を組み込んで,7006-7506-7556-7566-7576-7586-7606-7106の8両編成となっています。 (2024/03/20ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.50-38 1984年4月22日 7003F 7103他 6両 普通 須磨浦公園行 宝塚線 中津→十三 |
梅田 7003-7503-7563-7573-7603-7103 須磨浦公園 貫通扉中央に阪急ブレーブスマークを付けた7003F。1981年製造,初めてスイープファンが設けられ,クーラが全車とも中央よりに配置されているのもこの編成以降です。7003Fの編成は4M2Tでしたが,その後アルミ車両の7553,7583を中間に組み込み, 7003-7553-7503-7563-7573-7603-7583-7103のように,MM'ユニットの中間に新製アルミ付随車が入る構成となっていました。 (2024/03/20ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D70s_090101-49 (息子撮影) 2009年1月1日 7002F 7102 8両 特急 梅田行 神戸線 西宮北口 |
梅田 7002-7502-7552-7562-7572-7582-7602-7102 高速神戸 7002Fです。正雀工場でのバリアフリー等のリニューアル工事を受けており,冷房室外機の変化(鉄製→ステンレス製)と客室扉窓の大型化が目に付きます。 (2024/03/20ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D70s_090101-51 (息子撮影) 2009年1月1日 7003F 7103他 8両 普通 三宮行 神戸線 西宮北口 |
梅田 7003-7503-7553-7563-7573-7583-7603-7103 三宮 VRレンズで息子が手持ち撮影したコマ。多く登場している7003Fです。No.50-38と比べてみると,7103は密連に変更されており,グレー塗色も薄くなっています。ワイパーもブラックに。 (2024/03/20ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_111113-95 2011年11月13日 7006F 7106他 8両 特急 新開地行 神戸線 夙川→芦屋川 |
梅田 7006-7506-7556-7566-7576-7586-7606-7106 新開地 7006Fは屋根周りがアイボリー塗装になった程度の変更で運用されており,ほっとします。標識灯を点灯させて快走。 (2024/03/20ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_111113-102 2011年11月13日 7027F 7127他 8両 普通 三宮行 神戸線 夙川→芦屋川 |
梅田 7027-7527-7774-7767-7777-7764-7627-7127 三宮 4両目にラッキーナンバーの7777を含む7027F。 (2024/03/20ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_111113-136 2011年11月13日 7023F 7123他 6両 直通特急 嵐山行 嵐山線 松尾←上桂 十三 7023-7523-7763-7773-7623-7123 嵐山・高速神戸 秋の臨時ダイヤで高速神戸から嵐山に乗り入れるあたご。ヘッドマークで車両ナンバーが隠れています。 (2024/03/20ワイド化) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_120101-149 2012年1月1日 7009F 7109他 8両 特急 新開地行 神戸線 夙川→芦屋川 |
梅田 7009-7509-7559-7569-7579-7589-7609-7109 新開地 7109先頭で芦屋川へのスロープを登る7009F,クーラーが変更されています。 (2012/1/8追加 2024/03/20ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_120101-156 2012年1月1日 7027F 7127他 8両 特急 新開地行 神戸線 阪急六甲 |
梅田 7027-7527-7774-7767-7777-7764-7627-7127 三宮 初詣を兼ね阪急六甲の神戸行きホーム先端へ。冬の影が多い中,なんとか順光で撮影しました。 (2012/1/8追加 2024/03/20ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_120101-158 2012年1月1日 7019F 7119他 8両 特急 梅田行 神戸線 阪急六甲 |
梅田 7019-7519-7659-7669-7679-7689-7619-7119 新開地 大阪行き通過線を走行する7019F。クーラーはノーマルです。 (2012/1/8追加 2024/03/20ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_120101-164 2012年1月1日 7004F 7104他 8両 特急 新開地行 神戸線 阪急六甲 |
梅田 7004-7504-7554-7564-7574-7584-7604-7104 三宮 日が陰ってしまいましたので発色が落ちました。 (2012/1/8追加 2024/03/20ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_120101-166 2012年1月1日 7009F 7109他 8両 特急 梅田行 神戸線 阪急六甲 |
梅田 7009-7509-7559-7569-7579-7589-7609-7109 新開地 芦屋川で撮影した列車が新開地から戻ってきました。 (2012/1/8追加 2024/03/20ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_120103-218 2012年1月3日 7011F 7111他 8両 急行 梅田行 宝塚線 十三 |
梅田 7011-7511-7651-7661-7671-7681-7611-7111 宝塚 アルミ車体編成の7011F,宝塚向きの7111にも電気連結器を装備しています。 (2024/03/20追加) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_160102-030 2016年1月2日 7012F 7012他 8両 特急 新開地行 神戸線 芦屋川 梅田 7012-7512-7652-7662-7672-7682-7612-7112 新開地 芦屋川を通過する新開地行き特急 (2016/01/11追加 2024/03/20ワイド化) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_180815-496 2018年8月15日 7022F 7122他 8両 普通 神戸三宮行 神戸線 夙川→芦屋川 |
梅田 7022-7522-7676-7762-7772-7666-7622-7122 神戸三宮 久しぶりに芦屋川で撮影。7000系にも見るたびに相当手が入ってしまい新製当初の美しさが損なわれています。この7022FはVVVF化されています。 (2018/09/17追加) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_180815-501 2018年8月15日 7014F 7114他 8両 特急 新開地行 神戸線 御影→六甲 |
梅田 7014-7514-7556-7664-7674-7686-7614-7114 新開地 7014Fも前面貫通扉が大窓に改造されています。VVVF化編成。 (2018/09/17追加)  |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_180815-507 2018年8月15日 7019F 7119他 8両 特急 新開地行 神戸線 御影→六甲 |
梅田 7019-7519-7659-7669-7679-7689-7619-7119 新開地 この日は7000系が続々登場しました。VVVF化編成の7019Fも特急幕でやってきました。 (2018/09/17追加)  |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_180815-516 2018年8月15日 7009F 7109 8両 普通 神戸三宮行 神戸線 御影→六甲 |
梅田 7009-7509-7559-7569-7579-7589-7609-7109 神戸三宮 ようやくまともな7000系がやってきました。やっぱり貫通扉の窓のラインが揃って美しい。それからナンバーはここが落ち着きます。前照灯がなんか残念だけど,良かった。 (2018/09/17追加)  |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7006F 京とれいん 雅洛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_190430-199 2019年4月30日 7006F 京とれいん「雅洛」 7006他 6両 快速特急 梅田行 宝塚線* 十三-梅田 |
梅田 7006-7506-7566-7576-7606-7106 河原町 2編成目の京とれいん「雅洛」として改造された7006F。 (2019/06/23追加) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_190430-209 2019年4月30日 7006F 京とれいん「雅洛」 7006他 6両 快速特急 梅田行 宝塚線* 十三-梅田 |
梅田 7006-7506-7566-7576-7606-7106 河原町 標識灯の帯とパンタグラフを見ると反射的に6330Fかと思ってしまいます。 (2019/06/23追加)  |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_190430-215 2019年4月30日 7006F 京とれいん「雅洛」 7606他 6両 快速特急 梅田行 宝塚線* 十三-梅田 |
梅田 7006-7506-7566-7576-7606-7106 河原町 各車両の左右の客用扉は折り戸のようなデザインになり,中央の扉はきれいに埋められて丸窓になっています。 (2019/06/23追加)  |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_190430-219 2019年4月30日 7006F 京とれいん「雅洛」 7606他 6両 快速特急 河原町行 京都線内 |
梅田 7006-7506-7566-7576-7606-7106 河原町 上の写真撮影後C#7606に乗車しました。内装かなり凝ってます。無線LANも完備されており前面展望の動画をリアルタイムで自分のスマートデバイスで見ることができます。 (2019/06/23追加) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_190430-220 2019年4月30日 7006F 京とれいん「雅洛」 7606他 6両 快速特急 河原町行 京都線内 |
梅田 7006-7506-7566-7576-7606-7106 河原町 男性が立っている左側が客用扉で,つり革のある部分に座席があります。このC#7606はロングシートで,つり革の向こう側が中央の扉を埋めた部分。 (2019/06/23追加)  |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_190430-223 2019年4月30日 7006F 京とれいん「雅洛」 7606他 6両 快速特急 梅田行 京都線 河原町 梅田 7006-7506-7566-7576-7606-7106 河原町 7606の中央の扉を埋めた部分に座席を作るのではなく丸窓と石庭ができています。この落ち着いた雰囲気はインバウンドのお客さんに大ウケ。 (2019/06/23追加) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_190430-224 2019年4月30日 7006F 京とれいん「雅洛」 7106他 6両 快速特急 梅田行 京都線 河原町 |
梅田 7006-7506-7566-7576-7606-7106 河原町 7106の車両は向かい合わせのボックス席になっていました。 (2019/06/23追加)  |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_190430-224 2019年4月30日 7006F 京とれいん「雅洛」 7106他 6両 快速特急 梅田行 京都線 河原町 梅田 7006-7506-7566-7576-7606-7106 河原町 河原町駅の2番線に停車,折り返し準備中の7006F。すっかり京都線の車両になっています。 (2019/06/23追加) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*京都本線の起点は十三であり,梅田-十三間2.4kmは宝塚線の複々線扱いとなっています。 2009年7月25日 ページ作成開始 2009年8月15日 ページ公開 2009年11月28日 編成表作成 2011年11月19日 形式毎ページ分離 2012年1月8日 イベント毎昇順構成に変更 2024年3月19日 新製車一覧表を追加 2024年3月19日 編成表見直し 2024年3月19日 キャプション欄左右入替完了 2024年3月20日 各写真に編成を追記 2024年3月20日 Safariで半角数字列が電話番号リンクされるのを無効化 2024年3月20日 写真ワイド化完了 2024年3月20日 イベント毎昇順から形式番台毎時系列に並べ替え 2024年3月20日 新製車一覧表から写真へのリンクを追加 ■参考文献 ・神戸大学鉄道研究会編 丙線 第30号 阪急電鉄特集 1984年11月発行 ・篠原 丞 2000系から8000系に至る阪急電鉄新系列高性能電車の系譜 鉄道ファン 328 1988年8月号 ・篠原 丞 2000系から8000系に至る阪急電鉄新系列高性能電車の系譜 鉄道ファン 332 1988年12月号 ・阪急電鉄・諸河 久共著 日本の私鉄⑦ 阪急 カラーブックス 保育社 ・阪急電鉄開業100周年記念HANKYU MAROON WORLD 阪急電車のすべて 2010 阪急コミュニケーションズ ・山口益生 阪急電車 JTBパブリッシング 2012年 ・Wikipedia 阪急7000系電車 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
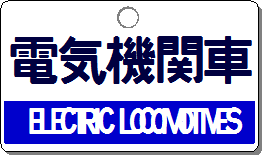 |
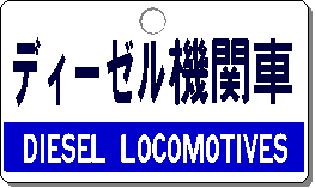 |
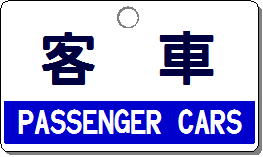 |
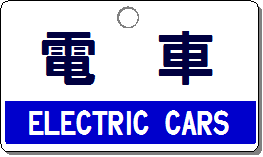 |
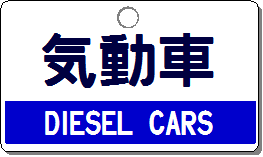 |
 |