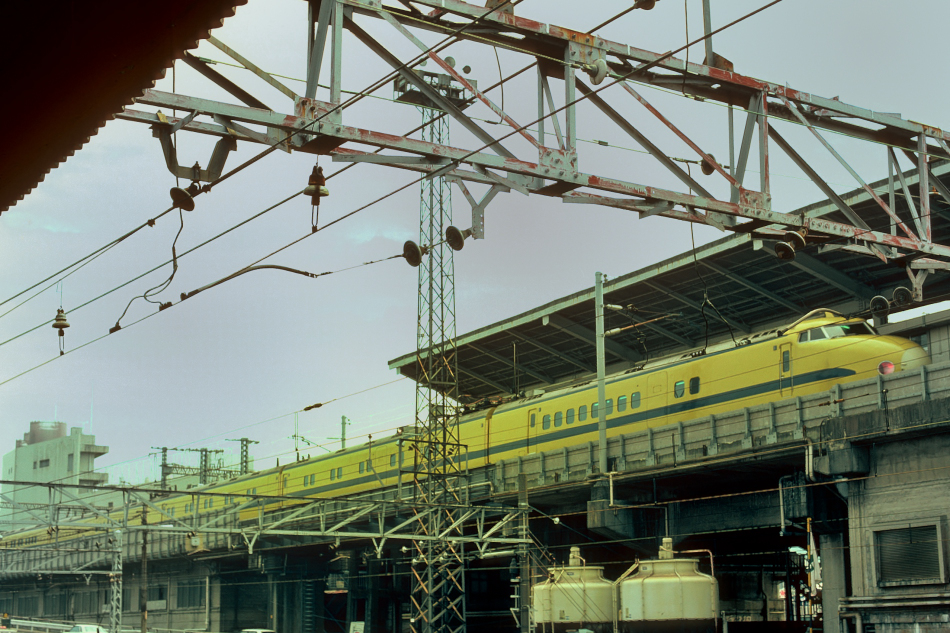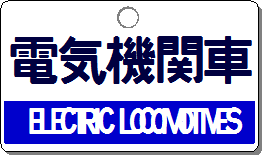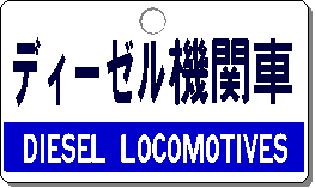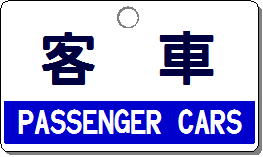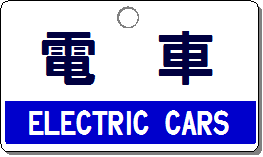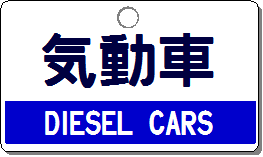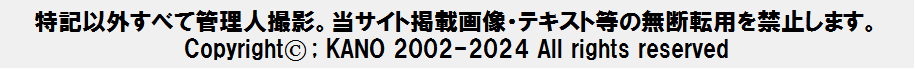| 形式 |
番台 |
番号 |
製造/改造年 |
仕様等 |
921形
在来線のマヤ検に相当する3台車装着の軌道検測車,牽引または編成に組み込み使用 |
0番台 |
921-1 |
1962年 |
在来線軌道試験車をベースに設計。剛性の高い車体に取り付けた3台車による相対変位から軌道の状態を測定する。当初4000形4001号として東急車輌で製造。前面非貫通3枚窓の箱型車体。鴨宮モデル線区に投入。新幹線開業時に921-1と改番。1978年から小山試験線に投入。1980年廃車,解体。 |
| 921-2 |
1964年 |
東海道新幹線開業に合わせ増備車として旧形客車マロネフ29 11を改造して製造。全長17.5m。1975年末廃車。1976年解体。 |
| 10番台 |
921-11
(T2編成) |
1974年 |
922形T2編成5号車。車体断面は922形と同一で車体長17.5mと短い。測定精度確保のため強固な鋼製車体で自重60t。 |
| 20番台 |
921-21
(T3編成) |
1979年 |
922形20番台T3編成5号車。車体断面は922形と同一で車体長17.5mと短い。測定精度確保のため強固な鋼製車体で自重60t。 |
| 30番台 |
921-31
(S1編成) |
|
925形0番台S1編成組み込み。921-11,21とほぼ同仕様。車体断面は925形と同一。東北新幹線向け雪切装置を追加。3台車のためボディマウント構造ではない。東急車輌製造。 |
921-32
(S1/S2編成) |
1997年改造 |
200系の中間車226-63を改造。レーザーによる測定を初導入。碓氷峠を抱える長野新幹線開業に伴い,軸重の関係で従来の3台車方式の軌道検測車では入線困難なため開発。S1編成またはS2編成に組み込んで使用。2002年12月8日付廃車。 |
| 40番台 |
921-41
(S2編成) |
|
925形10番台S2編成組み込み。921-11,21とほぼ同仕様。車体断面は925形と同一。東北新幹線向け雪切装置を追加。3台車のためボディマウント構造ではない。東急車輌製造。 |
| 922形 |
0番台 |
922-1
〜
922-4
T1編成 |
1964年改造 |
鴨宮モデル線の1000形B編成を電気・信号系の測定車に改造した初代ドクターイエロー編成。軌道系の測定は含んでいない。最高速度200km/h。のちにT1編成と呼称。1975年廃車解体。
| 1号車 |
922-1 |
Mc |
信号・通信測定車 |
| 2号車 |
922-2 |
M' |
電気測定車 |
| 3号車 |
922-3 |
M |
資材車 |
| 4号車 |
922-4 |
M'c |
電気測定車 |
|
| 10番台 |
922-11
〜
922-16
T2編成 |
1974年 |
T1編成老朽化と博多開業を控え0系をベースに新製された電気軌道総合試験車,T2編成。922形6両に軌道検測車921-11を加えた7両編成。日立製作所製。0系16次車と同時期発注で側窓は大窓。最高速度は210km/h。JR化以降はJR東海所属。923形T4編成登場で2001年運用終了,同年10月2〜5日に廃車解体。
| 1号車 |
922-11 |
Mc |
通信・信号・電気測定車 |
| 2号車 |
922-12 |
M' |
データ処理車 |
| 3号車 |
922-13 |
M |
電源車・観測ドーム |
| 4号車 |
922-14 |
M' |
倉庫・休憩室・寝台兼用シート |
| 5号車 |
921-11 |
T |
軌道検測車 (921形) |
| 6号車 |
922-15 |
M |
救援車・観測ドーム |
| 7号車 |
922-16 |
M'c |
架線磨耗測定車 |
|
| 20番台 |
922-21
〜
922-26
T3編成 |
1979年 |
T2編成の増備として新製されたT3編成。3-5号車は東急車輌製造,それ以外は日立製作所製造。0系1000番台27次車と同時発注のため側窓は小窓。JR化後はJR西日本所属。923形T4編成登場で予備車となる。2005年廃車。922-26が博多総合車両所で保存され,2011年以降リニア・鉄道館で展示保存。
| 1号車 |
922-21 |
Mc |
休憩室 |
| 2号車 |
922-22 |
M' |
データ処理・架線磨耗測定車 |
| 3号車 |
922-23 |
M |
電源車・観測ドーム |
| 4号車 |
922-24 |
M' |
倉庫 |
| 5号車 |
921-21 |
T |
軌道検測車 (921形) |
| 6号車 |
922-25 |
M |
救援車・観測ドーム |
| 7号車 |
922-26 |
M'c |
通信・信号・電気測定車 |
|
| 923形 |
0番台 |
923-1
〜
923-7
T4編成
|
2000年 |
東海道新幹線の300系以降の車両統一に伴い700系をベースに開発された,270km/hでの検測可能なドクターイエロー。1-3号車は日立製作所笠戸事業所,4-7号車は日本車輌製造。JR東海所属。高速化のため3台車による軌道検測をやめ,車体下部に設けたレーザー基準線と台車の光式レールセンサーとの相対変位検出方式に変更。軌道検測を担う4号車は他の車両と同じ2台車かつ車体長も25mと同一になった。
| 1号車 |
923-1 |
M1c |
変電/電車線/信号/通信測定台,電気/施設測定機器 |
| 2号車 |
923-2 |
M' |
高圧室,電気関係測定機器 |
| 3号車 |
923-3 |
M2 |
観測ドーム,電気倉庫,電力データ整理室 |
| 4号車 |
923-4 |
T |
軌道検測車 軌道計測室,施設データ整理室,施設倉庫 |
| 5号車 |
923-5 |
M2 |
多目的試験・電源供給,観測ドーム,休憩室 |
| 6号車 |
923-6 |
M' |
ミーティングルーム,高圧室,電気関係測定機器 |
| 7号車 |
923-7 |
M1c |
電気/施設測定機器,カラー大型ディスプレイ |
|
| 3000番台 |
923-3001
〜
923-3007
T5編成 |
2005年 |
2003年ダイヤ改正で高速化された東海道新幹線で922形T3編成での210km/hの検測運転が困難になったこととT3編成の老朽化も考慮して製造。T5編成。仕様はほぼT4編成と同一。JR西日本博多総合車両所所属。 |
| 925形 |
0番台 |
925-1
〜
925-6
S1編成 |
1979年 |
東北新幹線に向け200系をベースに製造されたドクターイエローS1編成。T3編成の50Hz版。塗色は黄色地に緑帯。軌道検測車は921-31。製造メーカは1,2号車が日本車輌製造,3,4号車が近畿車輛,6,7号車が川崎重工業。長野新幹線対応で軌道検測車を921-32に変更。E926形S51編成登場により2001年廃車。 |
| 10番台 |
925-11
〜
925-16
S2編成 |
1983年改造 |
1978年製造の試験車962形を改造した編成。窓のいくつかを埋めている。S2編成。組み込む軌道検測車は921-41。
東北・上越新幹線開業後,921-41を抜いた6両編成で高速試験車として使用され,200系による240km/h,275km/h運転が実施された。E926形S51編成登場により2003年1月25日付廃車。 |
| E926形 |
- |
E926-1
〜
E926-6,
E926-13
East i |
2001年 |
山形・秋田新幹線を含むJR東日本の新幹線全域をカバーするため,E3系をベースに開発された電気・軌道総合検測車で,East
iの愛称を持つ。最高速度は275km/h。3号車はE926-3とE926-13の2両があり,単独でも他編成に組み込んで軌道検測可能。E926-13は2015年2月4日廃車。
| 1号車 |
E926-1 |
M1c |
通信(LCX・在来線列車無線),電力(架線間隔測定),信号(ATC) |
| 2号車 |
E926-2 |
M2 |
通信・測定用電源 |
| 3号車 |
E926-3
E926-13 |
T |
軌道検測車 |
| 4号車 |
E926-4 |
M2 |
電力(集電・検測兼用パンタグラフ) |
| 5号車 |
E926-5 |
M1 |
電力・信号 |
| 6号車 |
E926-6 |
M2c |
電力(架線間隔測定),信号(ATC) |
|
| 941形 |
- |
941-1
941-2 |
1962年改造
1964年改造 |
鴨宮モデル線の1000形A編成を投入2ヶ月後の1962年8月に電気試験車に改造し,さらに1964年に救援車に改造した編成。最高速度200km/h。1975年廃車解体。
| 1号車 |
941-1 |
Mc |
資材室 |
| 2号車 |
941-2 |
M'c |
救援要員用座席(40席),工具棚 |
|