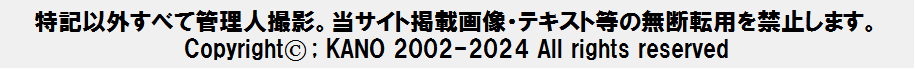|
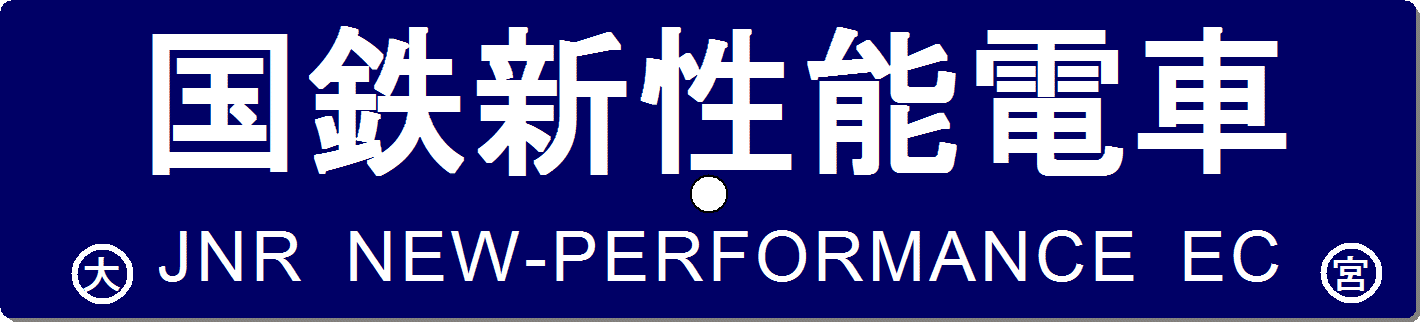 |
| 711系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【写真へ】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クハ711 901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.16‐22 1983年8月18日 8:30 札サウ S901編成他 クハ711‐901他 6両 室蘭本線 登別 |
小樽/奇 クハ711+モハ711+クハ711+クハ711‐119+クモハ711‐901+クハ711‐901
室蘭 試作車のクハ711‐901他の6連。サッシュの側窓は153系,165系,475系などを思わせます。 (2023/07/26ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クハ711 17‐36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.148‐7 1987年7月31日 札サウ S57編成 クハ711‐29他 3両 室蘭本線 苫小牧 |
小樽/奇 クハ711‐29+モハ711‐57+クハ711‐30 室蘭 くるくる電車ポプラ号の貴重な写真。1987年7〜8月の北海道の旅の1コマ。ようやく日時と場所特定できました。 (2010/01/31追記 2023/07/26ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クハ711 101‐120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.241‐32 1991年9月17日 札サウ S106編成 クハ711‐106他 3両 室蘭本線 白老→社台 |
小樽/奇 クハ711‐106+モハ711‐106+クハ711‐206 室蘭 札幌都市圏で増加する乗降客への対策として1987年からクハ711を3扉にする改造が施工されています。 (2009/04/04追加 2023/07/26ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.242‐3 1991年9月17日 札サウ S113編成 クハ711‐113他 3両 室蘭本線 白老→社台 |
小樽/奇 クハ711‐113+モハ711‐113+ クハ711‐213 室蘭 S113編成。この編成は3扉改造されていません。 (2009/04/04追加 2023/07/26ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クハ711 201‐218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.16‐21 1983年8月18日 6:23 札サウ S104編成 クハ711‐204他 6両 函館本線 札幌 |
小樽/奇 クハ711+モハ711+クハ711+クハ711‐104+モハ711‐104+クハ711‐204
旭川・室蘭 S104編成,クハ711‐204他の3連+3連。フィルムはKR。 (2023/07/26ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D200_090320‐44 2009年3月20日 6:38 札サウ S102編成他 クハ711‐202他 6両 121M 函館本線 札幌 |
小樽/奇 クハ711+モハ711+クハ711+クハ711‐101+モハ711‐102+クハ711‐202
旭川・室蘭 S102編成(クハ711‐202)他の3+3連。小樽5:38発,札幌6:26着(7番線)の普通列車。編成は異なりますが,すぐ上の写真No.16‐21とほぼ同じ場所,時刻。比較すると,JR化,高架化,塗色変更,冷改,パンタ換装などなど大きく変化しており,一方撮影者側の機材も銀塩カメラにマニュアルレンズ,ポジフィルムから,デジタル,AF,VR手振れ防止レンズと様変わりしています。撮影データは,ISO200,f5.6,1/5秒(手持)。四半世紀の時間が変えていったさまざまな事象を実感しながら今回ページをアップしました。 (2023/07/26ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D200_090320‐34 2009年3月20日 札サウ S102編成他 クハ711‐202他 6両 121M 函館本線 札幌 |
小樽/奇 クハ711+モハ711+クハ711+クハ711‐101+モハ711‐102+クハ711‐202
旭川・室蘭 札幌駅に到着する小樽からの121M列車 (2023/07/29追加) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D200_090320‐38 2009年3月20日 札サウ S102編成他 クハ711‐202他 6両 121M 函館本線 札幌 |
小樽/奇 クハ711+モハ711+クハ711+クハ711‐101+モハ711‐102+クハ711‐202
旭川・室蘭 快速エアポートとして活躍する721系F510編成との2ショット (2023/07/29追加) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009年3月22日 ページ新設 2009年4月4日 写真追加 2011年12月4日 キャプション追加 2023年7月26日 写真ワイド化完了 2023年7月26日 キャプション欄左右入替完了 2023年7月29日 新製車一覧表を追加 2023年7月29日 イベント毎昇順から形式番台毎時系列に並べ替え 2023年7月29日 新製車一覧表から写真へのリンク設置 ■参考文献 特集:交流電化開業40年 −20000V専用車両のあゆみ− Vol.37,No.432 鉄道ファン 1997年4月 交友社 JR電車編成表 '92年冬号 ジェー・アール・アール Wikipedia 国鉄711系電車 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
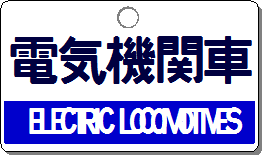 |
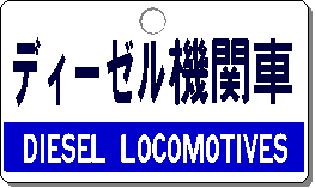 |
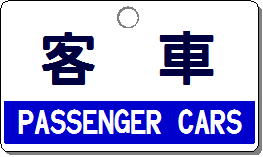 |
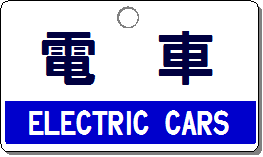 |
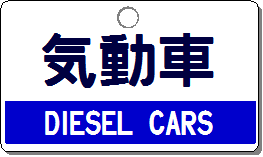 |
 |
|---|