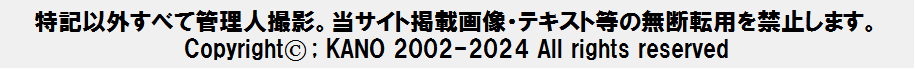|
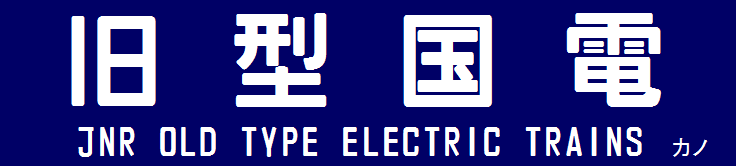 |
 |
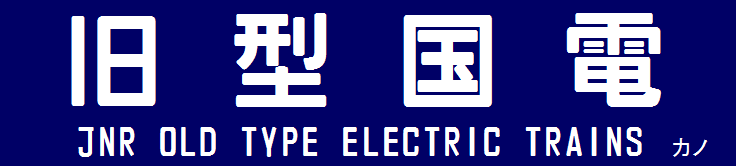 |
| 80系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クハ86001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_120103-247 2012年1月3日 クハ86001 交通科学博物館 80系の初期の姿,クハ86の最初の20両である86001-86020がこの顔で登場しました。この後に誕生した湘南形2枚窓マスクと比較するとシル・ヘッダーが正面に回り込んでおり,かなり重たい印象を受けますが,電車と言えばぶどう色かダークグリーンであった戦後の1949年にこのツートンカラーは画期的でした。 (2023/03/22ワイド化) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_120103-248 2012年1月3日 クハ86001 交通科学博物館 |
交科では京都駅の大屋根を移設し,その中に保存してありました。 (2023/03/22ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_170505-271 2017年5月5日 クハ86001 京都鉄道博物館 京都に引越ししてきたクハ86001。再塗装され新車の輝きを放っています。 (2017/05/20追加) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_170505-272 2017年5月5日 クハ86001 京都鉄道博物館 |
湘南色の塗装が美しい。 (2017/05/20追加) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_180502-074 2018年5月2日 クハ86001 京都鉄道博物館 人の少ない平日に出向いて撮り直しです。 (2018/05/12追加) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_180502-077 2018年5月2日 クハ86001 京都鉄道博物館 |
前照灯が大きく張り出しており,後期の2枚窓タイプとはまた大きく異なった古典的な顔をしています。 (2018/05/12追加)  |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モハ80001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_180502-078 2018年5月2日 モハ80001 京都鉄道博物館 |
今日の電車の隆盛を語る上で欠かせないエポックといえる,最古の中間電動車モハ80001の横顔。基本番台車の客室窓は旧型客車と差がありません。 (2018/05/12追加)  |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.D700_180502-233 2018年5月2日 モハ80001 京都鉄道博物館 |
モハ80001。シル,ヘッダー付きの一枚窓となっており,旧型客車に似ていますが自動扉です。この客室扉も制作年代ごとに桟が減り,徐々にすっきりした構造に進化していきました。 (2018/05/12追加)  |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クハ86300番台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.N8212-24 1982年11月20日 13:57 80系 4B 257M 飯田線 天竜峡←千代 |
4連で登場した80系が紅葉のトンネルに吸い込まれていきました。80系の先頭車クハ86は1950年度製の基本番台2次車から2枚窓に変更されました。この顔は湘南スタイルとして70系,EF58,東武キハ2000形,などさまざまな車両に影響を及ぼしました。クハ86では1951年度製から正面2枚窓のHゴム支持化され86300番台まで受け継がれました。 (2018/09/22 ワイド化)  |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.N8213-3A 1982年11月20日 20:40 クハ86300番台 4B 248M 飯田線 天竜峡 |
夜の天竜峡に到着した248Mは80系4両,湘南色のツートンは華やかさがあります。 (2018/09/22 ワイド化 2023/03/22シャドー調整)  |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.N8213-4A 1982年11月20日 20:43 クハ86319 4B 248M 飯田線 天竜峡 |
上と同じ編成の奇数(上り)向き,しっかり絞ってバルブ撮影。サボを変えるため線路側の扉も開かれています。 (2018/09/22 ワイド化 2023/03/22シャドー調整)  |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.N8213-7A 1982年11月21日 6:36 クハ86306 239M 飯田線 温田 |
温田にて,平岡発上諏訪行きの普通列車239Mと交換。駅員が運転士に通票キャリアを受け渡ししています。この列車,平岡6:24に出て上諏訪に10:31に到着するダイヤでした。クハ86300番台はそれまでの86100番台と異なり10系客車に準じたセミ・モノコック構造の全金属車体を採用,ウィンドウシル/ヘッダーを無くし窓が大型化しサイドビューがすっきりしました。内装も完全金属化され,当初から蛍光灯照明となり一気に近代化が進みました。 (2023/03/29 本ページに追加) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.N8213-20A 1982年11月21日 10:53 クハ86300番台 631M 飯田線 湯谷→三河槙原 |
貨物の後からやってきたのは80系4両編成の631M。豊橋9:40発,11:42中部天竜着のダイヤでした。 (2023/03/29 本ページに追加) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.N8213-31A 1982年11月21日 12:56 クハ86300番台 633M 飯田線 湯谷→三河槙原 |
下り80系中部天竜行き各停,望遠200mmで撮影。 (2023/03/22ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.N8214-3 1982年11月21日 14:28 クハ86300番台 6B 9632M 快速 奥三河 飯田線 三河槙原←柿平 |
槙原のお立ち台から撮影。80系4+2の6連で快走 (2023/03/22シャドー調整) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.N8214-9 1982年11月21日 16:45 左 クハ86309 4B 839M 右 クハユニ56003 4B1226M 飯田線 豊橋 |
左のクハ86はおでこの塗装の亀裂と運行番号表示窓左上の塗装の剥げ方からクハ86309と特定できました。 (2023/03/13ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クハ85100番台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.N8213-14A 1982年11月21日 8:30 左 クハ85108 4B 638M 右 クハ68409 2B 625M 飯田線 三河槙原 |
スカ色のクハ68と並ぶクハ85。飯田線には85104と85108がいましたが,運転席窓の高さが若干低いことからクハ85108であることが判明しました。前照灯下の手摺から正面窓の間隔を見ると区別できます。 (2023/03/13ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.N8213-27A 1982年11月21日 11:19 クハ85104 4B 1224M 飯田線 湯谷←三河槙原 |
飯田線では2両のクハ85100が83年まで活躍しました。クハ85104を最後尾にした1224Mが川沿いをゆく。 (2023/03/29 本ページに追加) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.N8214-13 1982年11月21日 16:45 クハ68410 4B 回1226M クハ85108 4B 839M 飯田線 豊橋 |
クハ68とクハ85。右側,17:15発の641Mが入線。この80系4連の編成はこの日の638Mと同じ,クハ85108を含む4両編成でした。 (2015/03/19追加 2023/03/22シャドー調整) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クモニ83100番台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.N8212-14 1982年11月20日 10:25 クモニ83103 1221M 飯田線 飯田 クモニ83100番台は飯田線の荷物車不足を補うためクモユニ81形の郵便室を撤去し,クモニ83形100番台とした改造車で,1969年に浜松工場で3両が改造され在籍していました。[57-5 浜松工]と記載された表記が標識灯のすぐ右脇にあるのが83101と83102であり,一方この表記がタイフォン側に寄っているのが83103,という違いがありました。したがってこの写真はクモニ83103だとわかります。なお2両目の車両はクハユニ56っぽいです。 (2023/04/05 郵便・荷物車のページから移設) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.N8212-37 1982年11月20日 19:50 左 クモニ83101 1227M 右 クモニ83103 1232M 飯田線 天竜峡 |
乗務員が降りたのを見計らってスピードライトを焚いてなんとか撮影。右側は昼間に飯田で交換したクモニ83103,左は83101です。 (2023/04/05 郵便・荷物車のページから移設) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年10月6日 飯田線旧型国電からページ分離 2023年3月13日 キャプション欄左右入替完了 2023年3月22日 写真ワイド化完了 2023年3月29日 新製車一覧表を追加 2023年3月29日 改造車表(撮影分のみ)を追加 2023年3月29日 新製車一覧表および改造車表から写真へのリンクを設置 2023年3月29日 Safariで半角数字列が電話番号リンクされるのを無効化 2023年4月5日 クモニ83100番台につき郵便・荷物車ページの写真を削除し本ページに移設 ■参考文献 沢柳健一 旧型国電50年(Ⅱ) JTBキャンブックス 手塚一之,浦原利穂 半流43系姉妹の一代記 鉄道ファン 1998年10月号-11月号 交友社 手塚一之 流電52系姉妹の一代記 鉄道ファン 1999年9月号-2000年1月号 交友社 浦原利穂 関西ファンの記録から 鉄道ファン 1999年9月号,10月号 交友社 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
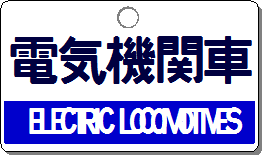 |
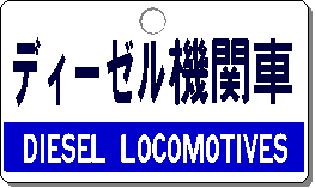 |
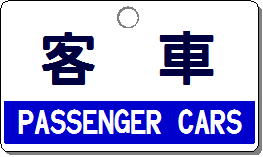 |
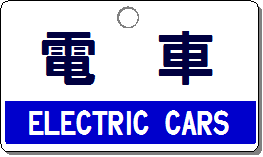 |
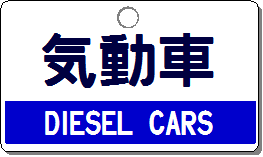 |
 |
|---|