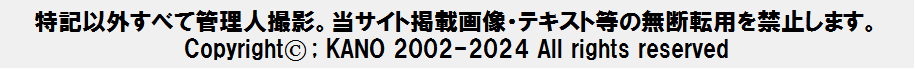|
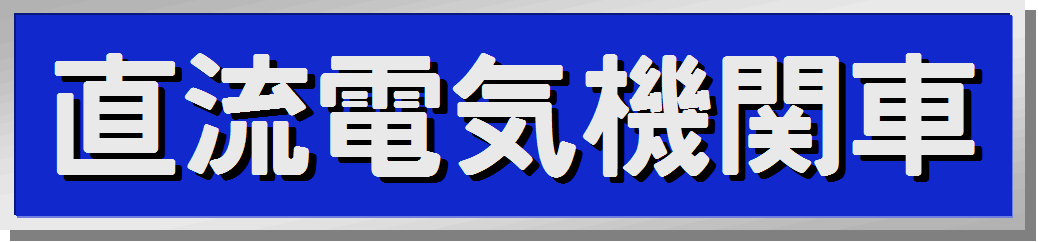 |
 |
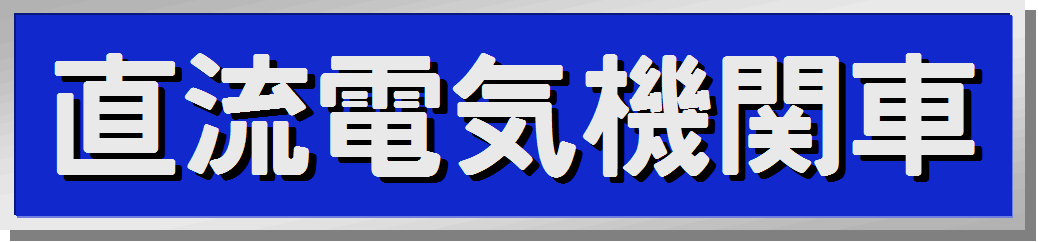 |
| ED60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ED60 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.64-11 1984年8月1日 ED62 1,ED60 1 浜松機関区 |
きかんしゃ大集合で顔を揃えたDクラス直流機のトップナンバーたち。1〜3号機は北松本支区に配置されていた関係で,竜華配置の4〜8号機と異なりヘッドライトが原形で美しい。 (2023/01/21ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.64-13 1984年8月1日 ED60 1,EF15 168 浜松機関区 |
EF15168と並んだED601。 (2023/01/21 このページに追加) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ED60 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.51-32 1984年5月5日 ED60 4+貨 紀勢本線 和歌山(操) |
竜華機関区には4〜8号機の5両が配置されていました。963レとしてEF1558の次位で和歌山(操)に到着したED60 4。今度は単機でタキ列車に連結され出を待っています。 (2023/01/21ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.104-25 1985年7月21日 ED60 4+EF1558+12系+マニ 阪和線 新家←長滝 |
重連ミステリーリレー号の先頭を務めるED60 4号機。 (2023/01/21ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ED60 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.115-11 1986年1月13日 配6981レ ED60 5 東海道本線 西ノ宮 |
EF66に引かれたED60 5の廃車回送です。鷹取工場への入場スジとして有名な6981レにて西ノ宮停車中,夕焼けに見送られての最後の旅です。編成はEF66+EF651+ヨ8000+ED605でした。 (2023/01/21ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.115-15 1986年1月13日 ED60 5 配6981レ 東海道本線 西ノ宮 同じくヨに連結された1位側。夕刻のバルブのため,空の色がとっても怪しく写りました。 (2023/01/21ワイド化) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ED60 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.97-9 1985年4月2日 ED60 6+EF15+コキ 阪和線 新家→長滝 |
EF15と組みコンテナ列車を牽引する6号機。 (2009/03/16追加 2023/01/21ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.104-21 1985年7月21日 ED60 6+ED60+コキ 阪和線 新家←長滝 |
阪和貨物を重連で牽引するED60。先頭は6号機。 (2023/01/21ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.105-32 1985年8月24日 EF15 58,ED60 6 吹田機関区 |
吹田機関区公開にて僚友EF15 58と肩をと並べるED60 6号機。ここに並べられた機関車はEF58
127,EF60 501,EF65 1001,EF81 1,EF66 1などなど馴染みの顔ばかり。こうしたカマは寂しいことにこの時期次々と本線上から去っていきました。 (2023/01/21ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ED60 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.57-20 1984年7月12日 ED60 7+DE10 1088+ヨ8000 +トムラ+オハ50+ヨ6000 京都 |
この変てこな編成は奈良線電化のための試験列車で,ちょうど京都に到着したところ,これから機回しです。 (2023/01/21ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.57-29 1984年7月12日 ED60 7 京都 |
機回し後のED60 7のサイドビュー。全長13m。生まれながらのショーティー。京都タワーの足元も望める一時代前の風景です。 (2023/01/21ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.57-38 1984年7月12日 ED60 7 奈良線 宇治←黄檗 |
宇治橋を渡る試験編成。ED60の前の黒いのは宇治川の鳥さんです。 (2023/01/21ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ED60 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.51-20 1984年5月5日 ED60 8+EF15 123+コキ 961レ 紀勢本線 和歌山→和歌山(操) |
EF15123を従えて和歌山(操)に到着するED60 8号機。コンテナを満載して堂々の走りっぷりです。 (2023/01/21ワイド化) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年12月24日 ページ新設 2023年1月21日 形式一覧表を追加 2023年1月21日 写真ワイド化完了 2023年1月21日 キャプション欄左右入替完了 ■ 参考文献 特集:国鉄の新形直流電機 鉄道ファン186 1976年10月号 交友社 Wikipedia 国鉄ED60形電気機関車 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
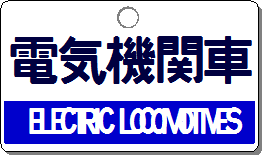 |
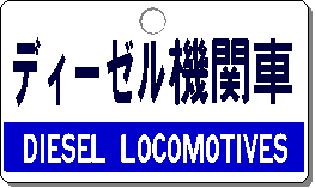 |
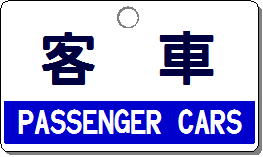 |
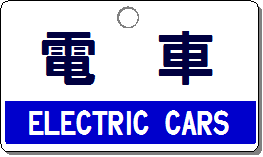 |
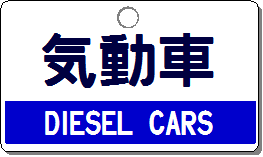 |
 |
|---|